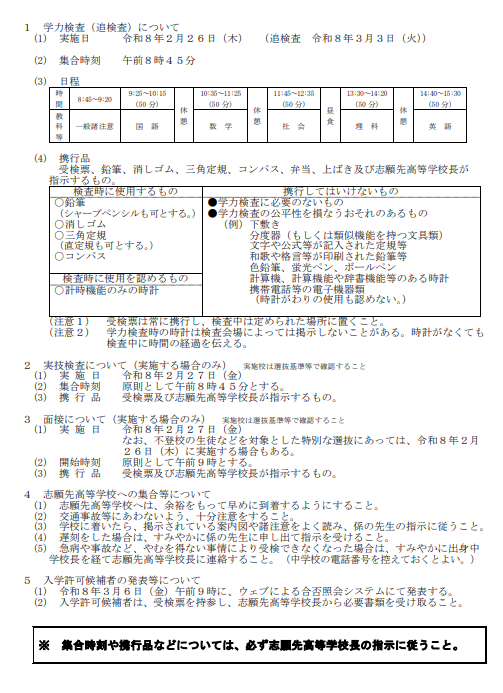こんにちは!和光南校の大柴です!
明日はクリスマスですね!街のあちこちでイルミネーションを見かけるかと思います。自分は今月頭に横浜へイルミネーションを見に行きました!
特に理由はないのに、
「なんかきれい」「ずっと見ていられる」
と、こんな風に感じたことはありませんか?
実はこの感覚、気分や雰囲気だけではなく、脳の働きが大きく関係しています。
今回は、イルミネーションがきれいに見える理由を理科+ちょっと心理の視点で見ていきたいと思います。
理由① ~暗い場所では「光」が目立つ~
夜のイルミネーションが特にきれいに見える理由の一つは、周りが暗いからです。
暗い場所では、「明るいもの・光っているもの」が、昼間よりもはっきり目に入ります。
これは、目の中にある光を感じ取る細胞(視細胞)が、暗いときほど敏感になるからです。
理由② ~色は脳に直接影響する~
イルミネーションには、白だけでなく、青・赤・黄色・緑など、さまざまな色が使われています。
実は色には、それぞれ人の気分に影響を与える特徴があります。
青:落ち着く・安心する
赤:元気になる・目立つ
黄:楽しい・明るい
といったものです。
脳はこれらの色を見た瞬間に、
無意識のうちに「心地いい」「楽しい」と判断しています。
理由③ ~脳は「変化」に弱い~
イルミネーションと言えば、、
光が点いたり消えたり、色がゆっくり変わったり
と、ずっと同じではありません。
実は脳には、変化のあるものに自然と注意を向ける性質があります。
そのため、動きのある光を見ると、つい目で追ってしまうのです。
なぜ夜の光に惹かれるのか?
人間はもともと、「夜 → 視界が悪くなる&危険を見つけにくい」という状況で生きてきました。
そのため、暗い中で光を見つけると、脳が「大事なものかもしれない」と反応します。
つまり、夜の光=本能的に気になる存在というわけです。
理科:光・明るさ・色
保健/心理的分野:感覚・脳の働き
「きれい」「好き」という感覚も、
理科的に説明できると面白くなります。
✨ まとめ
:イルミネーションがきれいに見えるのは脳の働き
:暗さ・色・変化がポイント
:感覚にはちゃんと理由がある
今の期間、何気なく見ているイルミネーションも、
少し視点を変えるだけで立派な“学びの題材”になります。
これからの冬はぜひ、「これ、脳はどう感じてるんだろう?」
そんなことを考えてみるといつもと違った楽しみができるかもしれませんね。